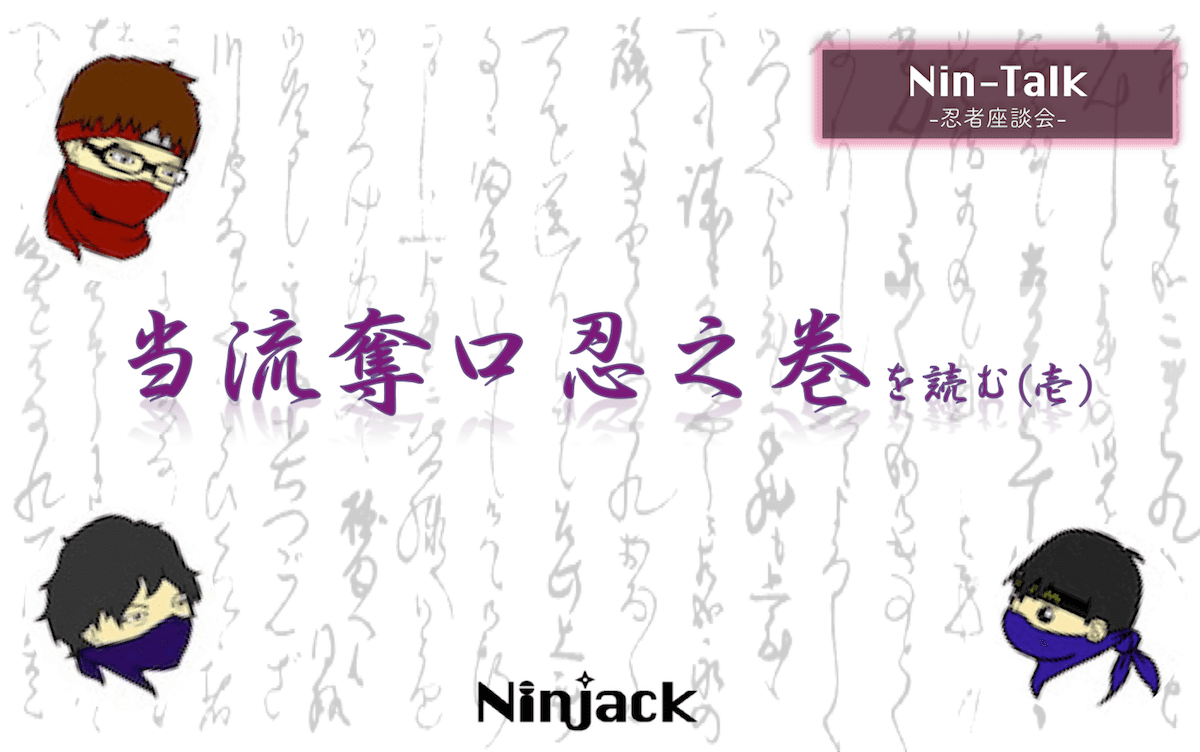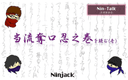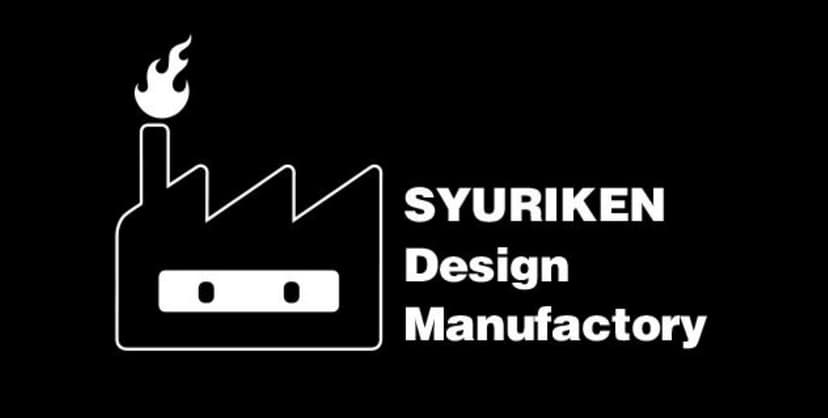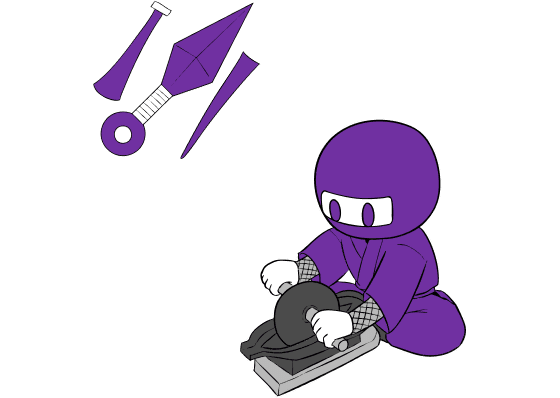どうも、Ninjack編集忍です。 このすべての忍者をJackするとかいうちょっとおかしい忍者専門メディア「Ninjack」も、読者のみなさまのおかげで運営開始してから1年半が経とうとしています。
NinjackはほとんどNinjack編集忍ひとりで運営しているのですが、困った時に様々な面でご協力いただいている忍者の方たちがおりまして、突然ですがそんなNinjackに忍ぶ助っ人忍者の方達をご紹介したいと思います。

とみ丸
某大手テクノロジー会社に勤務しながらも、忍者が大好きすぎるTech忍者。Ninjackの特派員としてたまに記事のための情報収集などをしてくれる。Ninjackへのハッキング対策や各種設定などいつも手伝ってくれるエンジニア忍者で、自信でもiPad掛け軸や忍者刀ライトサーベルなどNEO忍具の開発に余念がない。家の部屋で手裏剣打ちができるように改造して練習してたら部屋がボロボロになったらしい。

直之進
大学を卒業して今年就職したばかりの新社会人忍者。しかしその本当の姿は、忍者界で最も若い研究家として活躍する忍者界の重鎮。Ninjackの忍者歴史考証記事のネタなどをたまに持ってきてくれる。年下なのに古文書も読めるし知的で頼もしい忍者。
3ヶ月に1回くらい飲み会で会うくらいなのですが、こちらの面々がNinjackをお届けするNinjack編集部でございます。
本日はこんなNinjack編集部の忍者軍団でたまに行うNinjack編集会議(と銘打ったただの飲み会)で上がった企画をお送りしたいと思います!
その名も「Ninjack編集部で忍術書を読んでみて、好き勝手突っ込んでみよう」企画です。
「当流奪口忍之巻」を読んでみよう
直之進「みなさん!江戸時代初期に書かれたと言われる忍術伝書「当流奪口忍之巻」という忍術をご存知ですか!?」
とみ丸「トウリュウダッコウシノビノマキ…山田雄司先生の授業とかで聞いたことある!」
たかまる「拙者も名前は聞いたことあるけど、中身はあんまり詳しくないんだよね〜。」
直之進「そんなみなさんのために今日は現代語訳にして持ってきたので、一緒に読みましょう!全部ではないのですが面白そうなところだけピックアップしています!」
たかまる「おぉ、さすが研究忍!よろしくお願いします!」
序文には何が書かれている?
直之進「さて、序文とも言うべき最初には、このようなことが書かれています。」
序文
この当流とは楠流のことで、奪口とは忍びのことである。この「口を奪う」と書くのには、3つの理由がある。1つ目は日本国中の地方の人々の言葉をよく真似できるから。2つ目は他人の喋り方を真似することができるから。そして3つ目は、人の言葉を自分の利とするからである。自分の利にするというのは、他人が良いことや賢いことを言ったそのとき、たとえ自分には思いつかないようなことであっても「実は私も、そう思っていたところです」などと言うことである。
とみ丸「3つ目の「いやぁ、俺もそう思ってたんですよ」って乗っかってる感じが汚いね(笑)さすが忍者、汚い!」
たかまる「これは…奪われた方はムカつくねw ちなみに不意にキスをすることも奪口なんじゃない?」
直之進「編集忍さん、それはただのキス魔なので違います。さて次は「忍」の一字に込める筆写の魂が書かれていますよ。」
たかまる「ツッコミが厳しい…」
忍の一字
「忍」の字は、刃の下に心を書く。自分の胸に白刃を当てて物を問い、決断する。そういう精神のことである。古語にも「百戦百勝、一忍に及ばず」という。「忍」の一字をよく心得ることである。
たかまる「百戦百勝、一忍に及ばず!忍ぶ方が勝つよりもずっと大事ってことかぁ。かっこいいなー忍者っぽくて!」
とみ丸「うん、すっごいカッコいい感は伝わるんだけど、冷静に考えると何言ってるのかよくわかんないところがいいね!」
五忍の教えとは?
直之進「「当流奪口忍之巻」には忍生・忍死・忍欲・忍我・忍人と「五忍の教え」なるものが書かれています!」
忍生
「忍生」というのは、五忍の第一で「生を忍ぶ」ということである。死ぬほどツライことや恥ずかしいことがあっても、死を避け、生を“忍ぶ”のである。また「生を養う」ことも重要だ。飲食色欲にまみれては生を養うことはできず、酒を飲めば欲にかられてしまう。上司の言うことや友人との交わりでも、生を養うのに害することであれば、恥も謗(そし)りをも忍ぶ必要があるのだが、とはいえ、これがなかなか難しい。
とみ丸「うーん、これすっごいわかるね。昔の忍者も今と同じような悩みがあったんだなぁ。理不尽な人はいつの世にもいるんだね!」
たかまる「なんか最近似たような言葉を聞いたような気がする。「逃げるは恥だが役に立つ」って…それにしてもガッキーかわいいよね。ポッキーダンスの頃から好きだったんだけどさ、ハナミズキの映画とかも最高だっ…」
直之進「嵩丸さん真面目にやってもらっていいですか。さて次は「忍我」を見てみましょう!」
忍我
「忍我」というのは、少しも我を立てないことを言う。たとえ人に対して言いたいことがあっても、自分を立てず、人次第になることである。この心無くして、出世の道はない。
直之進「深い…!これは深いぞ…!!」
とみ丸「社会人1年目の直くんになんか響いてる…。結構これ大事だよね。」
たかまる「正忍記の「人を破らざるの習い」とか似た思想かもね!あ、でも次にこんなん書いてある。」
忍人
「忍人」は「忍我」の裏である。自分が言いたいことは少しも恐れること無く、人にへつらうことなく、また人に従わず、おのれの心のままに我を立てることである。
直之進「忍人と忍我、どっちを守ればいいんでしょうか…(困惑)」
とみ丸「「対面は人に合わせたとしても、自分の本心は曲げるな」ってことかな。いざという時には耐えなくていいんだろうね。」
たかまる「「身体は売っても心は売るな」って話だろうね。直くん、よく覚えておこう!」
直之進「身体も売らないですよ?」
五忍を習得している人は?
右の5箇条は忍の大事であるが、全てを得ている人はいない。しかし一つ一つは得ている者がいるので、そういう人を見立てることが重要である。これを当流五忍という。
とみ丸「結局誰も習得していないんだ(笑) 忍者だったら身につけてるのかと思ったのに!」
いよいよ具体的な忍術の説明がはじまる!
直之進「さあ、お待ちかね忍術の解説です!」
忍者をもっぱら常に用いるべきこと
実は、この言葉には2つの意味がある。1つは常に用いること、もう1つは「常を用いる」ことである。「常を用いる」とは、忍ぶときに平静を装うことで、人は忍びに気づくことができない。なお、「常に用いる」とは、日常生活の中で(忍術を)心掛けることである。
たかまる「よく部活とかで「本番のように練習して、練習のように本番に臨め」とか指導されたけどそれと同じだね!」
とみ丸「でも書き方がこれぞ秘伝書って感じだから、顧問の先生に言われるよりもありがたみが数段違うね。」
忍ぶ場を踏むべきこと
忍び入ろうと思う所は、あらかじめよく知っておくことが大切である。それができないときは、絵図を見てから忍ぶと良い。
とみ丸「すっごく当たり前な事書いてある!笑」
たかまる「忍びこむ前に♪ 地図とか見てから♪ ・・・忍ぼう♪ あたりまえ体操〜♪」
追従軽薄用捨のこと
これは人に対して、気に入ってもらうために、好きでないものを好きであるように見せることである。武士はそんなことはしないが、そんなプライドは捨てるべきである。でなければ、気の赴くままに人と交わることはできない。時と場合と対象の人によって、対応を変える必要があるだろう。
直之進「今も昔も同じなんですね。」
とみ丸「忍術書だと深く聞こえるんだけど、普通のサラリーマンとかが言うとなんかこう、切ない感じになってくるね。」
一騎打の場(敵の人数の見積り)のこと
これは敵の人数を見積もるために、広い場所に目の良い者を2人ばかり置いて、五色の豆などを器に入れておく。馬なら青い豆、徒歩は白い豆、足軽は黄色の豆という具合に、色を分けて別の器へ入れ、最後にそれぞれの色の豆の数を数えれば人数がすぐに分かる。
直之進「忍者の道具として知られる「五色米」みたいですね。興味深いです!」
とみ丸「でも結局最後は地道に豆の数を数えなきゃいけないんだね…馬役、徒歩役、足軽役に3人で役割分担して数えればいいんじゃ…」
たかまる「それは!言わない!お約束!」
問えば答えず、語れば落ちるのこと
何事でも、問い尋ねても人は喋らないものである。まず問わずに、それとなく他のことから語っていれば、向こうから思わず言うものである。
たかまる「語れば落ちる!これは気になる女の子をクドくのに使えますな!」
直之進「うーん、なんか違う気がします!」
とみ丸「聞きたいことは自分のことから話して「あなたはどうですか?」って聞くといいってよく言われてるよね。現代に通じてる感があっていいなぁ。」
己を禁ずるときは人をもってなすこと
自分が忍び込むことが、敵方にバレてるときは、他の人に忍び込んでもらうと良い。
たかまる「いやいやいや、そりゃそうでしょ!笑」
直之進「みんなが世代か分かりませんが、「学校へ行こう!」のチゲ&カルビを思い出したのは僕だけじゃないはず…」
とみ丸「わかんないから検索しよう… 「学校へ行こう チゲ&カルビ」と…」
我より上智・下愚を知ること
人の上智を見抜くには、人に「これこれについてどう思うか」と意見を聞く。それが自分の考えよりも良ければ上智、悪ければ下愚である。何度も試みるのが良い。
直之進「うわーー!すごく上から目線だ!!」
たかまる「聞いたときに「そうですねぇ、まずあなたはどう思いますか?」って聞き返されちゃったら、立場逆転して自分が試されちゃうけどね!」
心妙術を好むこと
人は常に妙術・不思議を好むものである。由井正雪が京都山科を通ったとき、人家に「ツバメ石」なる石があった。春に雨降ればこの石はツバメとなって空を飛び回ると噂され、人々が群衆を成していたという。これを見て、人心とは拙(つたな)く、妙術を好むと悟ったらしい。
直之進「由井正雪は、江戸初期の人物で、江戸幕府転覆を謀った人物です。さて、人は常に妙術・不思議を好む。これは現代でも当てはまりそうですね。」
たかまる「「手相を見てあげるよ」って言ったら、どんな女性の手でも握れるしね。」
とみ丸「ちょっと違うような…?」
直之進「だいぶ違いますね(笑)」