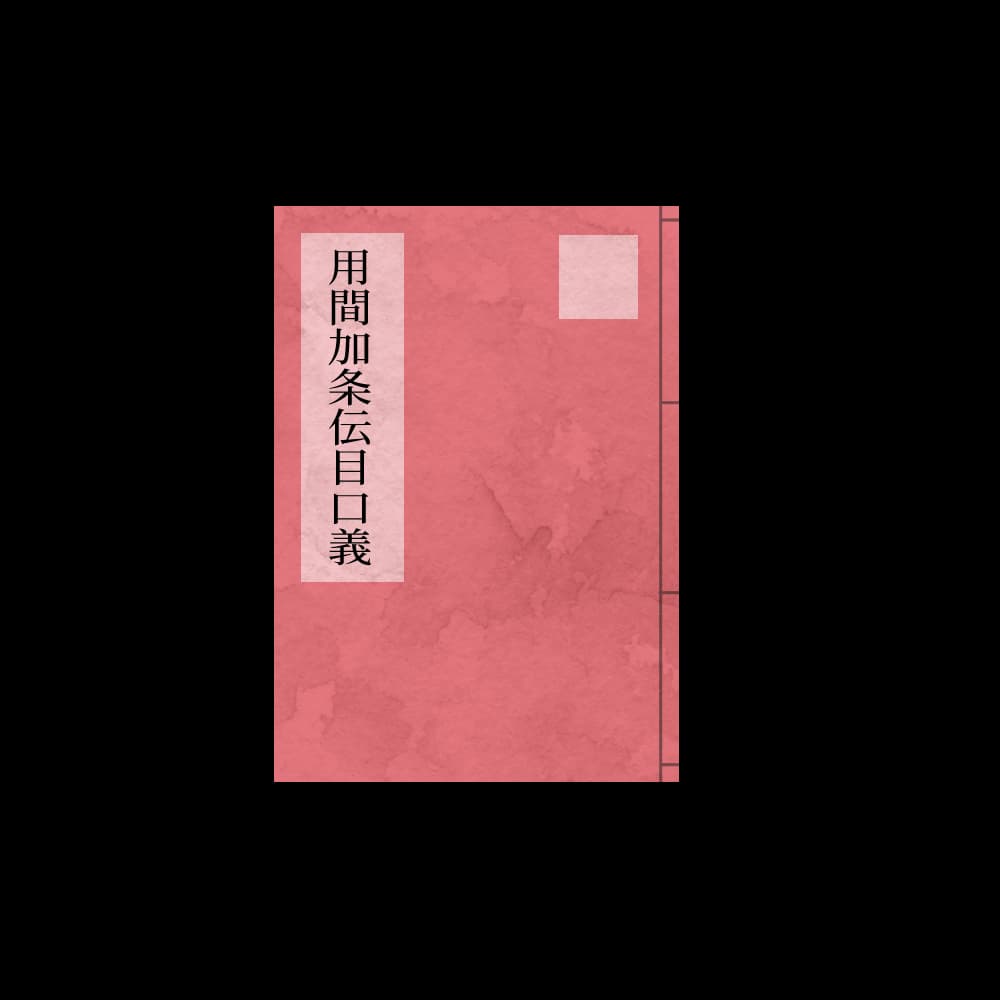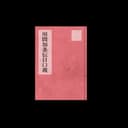甲賀と伊賀、それぞれの差が一目瞭然
『用間加条伝目口義(ようかんかじょうでんもくくぎ)』は、元文二年(1737年)に尾張藩の軍学者である近松彦之進茂矩が、甲賀に伝わった伝書『加条』と伊賀に伝わった伝書『伝目』のうち6〜7割をまとめた忍術書である。甲賀の忍術は尾張藩の御忍役人としても有名な木村奥野介康敬、伊賀の忍術は服部頼英から口伝を受けて、筆記を特別に許された。『加条』『伝目』の残りの3〜4割は秘伝のため掲載されていない。 上下巻の二巻構成。
内容は諜報・潜入・遁走といった忍術らしい忍術が多い。特徴的なのは内容の書かれ方であり、一部の項では同じ名前の忍術でも、「甲賀伝曰」「伊賀伝曰」と、それぞれの地域でどのように伝わってきたのかが明確に差別化されていることである。例をあげると、忍びの起原について、伊賀ではスサノオノミコトが忍術を使用したことがはじまりとされており、甲賀では、はじめに忍びとして働いたのは雉であると残されている。
もう一点の特徴は、下巻の『加条』項目が三重相伝という方法で記されており、これは初・中・後の三段階に分けて段階的に内容を深めていく手法。初伝ではにわかに信じがたい呪術や表面的な内容を伝えて反応を観察し、素質のある者を見極めて本質を伝えるためだと言われている。
「まず初伝を読み、後伝はどうなっているか予測する」「伊賀伝を読み、甲賀伝を予測する」などクイズ形式でも楽しめる、パーティにも適した忍術伝書。
『用間加条伝目口義』記載の忍術の解説や、他忍術書との横断検索も可能な忍術・忍器データベースはこちら